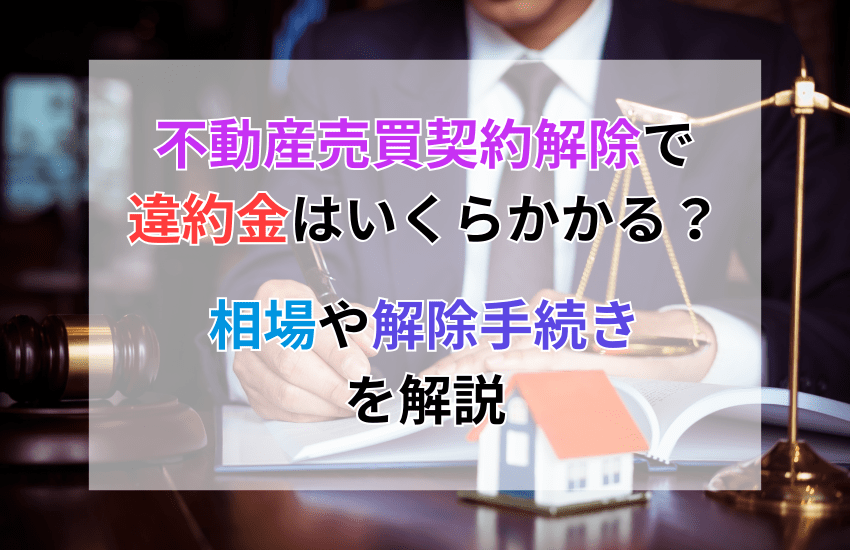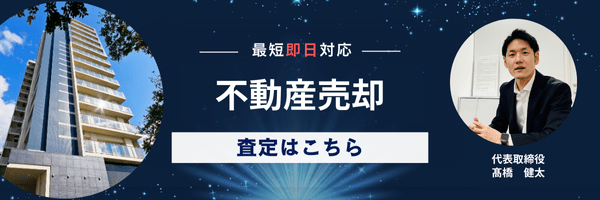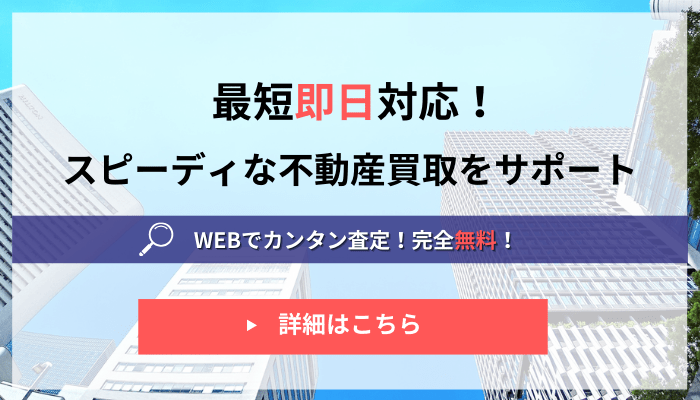「不動産売買契約の解除で違約金はいくらかかる?」そんな不安を抱えていませんか?この記事では、違約金が発生するケース、相場、解除手続きの方法を具体的に解説。発生しないケースや手続きの注意点まで網羅的にご紹介します。
不動産購入は金額も非常に大きく、慣れない手続きに戸惑うことも少なくないでしょう。
不動産取引について正しい知識を得て、予期せぬ高額な違約金に焦らず、冷静に問題解決へ導くヒントを得ましょう。
不動産売買契約の解除で違約金が発生するケースとは
不動産売買契約は、一度締結すると原則としてその内容に拘束されます。しかし、何らかの事情で契約を解除せざるを得ない状況に陥ることも少なくありません。その際、契約解除の理由や方法によっては、相手方に対して違約金を支払う義務が発生することがあります。
この章では、不動産売買契約の解除において、どのような場合に違約金が発生するのか、その具体的なケースについて詳しく解説します。
違約金とは何か 損害賠償との違い
不動産売買契約における「違約金」とは、契約に違反した場合に、その違反をした側が相手方に対して支払うことをあらかじめ契約で定めた金銭を指します。多くの場合、違約金は「損害賠償額の予定」としての性質を持ちます。
一方、「損害賠償」は、契約違反によって実際に生じた損害を補填するために支払われる金銭です。損害賠償を請求する側は、損害が発生したこと、その損害が契約違反によって生じたこと(因果関係)、そして損害の具体的な金額を立証する必要があります。
契約解除の種類と違約金の関係
不動産売買契約の解除にはいくつかの種類があり、それぞれ違約金の発生条件や取り扱いが異なります。主な解除の種類と違約金との関係を見ていきましょう。
手付解除の場合
手付解除とは、売買契約締結時に買主が売主へ支払う「手付金」を用いて契約を解除する方法です。手付金には、契約の成立を証する「証約手付」、契約解除権を留保する「解約手付」、そして債務不履行があった場合の違約金に充当される「違約手付」といった性質があります。
不動産売買契約においては、特段の定めがない限り、手付金は「解約手付」としての性質を持つとされています。
手付解除の場合、手付金自体が解除料としての役割を果たすため、原則として別途の違約金や損害賠償は発生しません。これは、手付金が契約の「解約料」として機能しているためです。
不動産購入時の手付金の役割について知りたい方は「不動産購入の基礎知識!買付証明書と手付金の役割を解説」の記事をご参照ください。
債務不履行による解除の場合
債務不履行による解除とは、売主または買主のどちらか一方が契約内容(債務)を履行しない場合に、相手方が契約を解除することです。
債務不履行による解除の場合、契約書に「違約金特約」が定められていれば、その特約に基づいて違約金が発生します。違約金特約がない場合でも、債務不履行によって実際に損害が生じた場合は、損害賠償を請求することが可能です。
債務不履行の主な例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 履行遅滞
約束の期日までに代金の支払いや物件の引渡しが行われない。 - 履行不能
契約の目的物が滅失するなど、債務の履行が不可能になった。 - 履行拒絶
債務者が明確に債務を履行しない意思表示をした。
債務不履行による解除は、原則として、相手方に相当の期間を定めて履行を催告(請求)し、その期間内に履行がされない場合に可能となります。ただし、履行が不可能である場合や、相手方が明確に履行を拒絶している場合は、催告なしに解除できることもあります。
特約による解除の場合
特約による解除とは、売買契約書に記載された特定の条件(特約)が成就しなかったり、満たされなかったりした場合に、その特約に基づいて契約を解除することです。このような特約が契約書に明記されている場合、その条件が満たされなかった際には、特約の定めに従って違約金が発生します。
ただし、特約の中には、買主のローン特約のように、解除された場合に違約金が発生しない旨が明記されているものもあります。特約による解除の際は、契約書に記載された特約条項の内容を詳細に確認することが極めて重要です。
合意解除の場合
合意解除とは、売主と買主の双方が話し合い、お互いの合意に基づいて契約を解除することです。
合意解除の場合、違約金の有無や金額、その他、既に支払われた金銭(手付金、中間金など)の精算方法については、当事者間の話し合いによって自由に定めることができます。
合意解除を行う際は、後々のトラブルを避けるためにも、解除の条件、金銭の精算方法、その他一切の権利義務の消滅について、書面(合意解除契約書など)で明確に合意しておくことが重要です。
不動産売買契約解除の違約金相場

不動産売買契約の解除に伴う違約金は、その発生ケースや契約内容によって大きく異なります。ここでは、違約金の一般的な相場について詳しく解説します。
違約金の一般的な相場
不動産売買契約における違約金は、契約書にその取り決めが記載されていることがほとんどです。特に、手付金が違約金として機能するケースが一般的です。手付解除の場合、買主が契約を解除する場合は手付金を放棄し、売主が契約を解除する場合は手付金の倍額を買主に支払うのが通例です。
手付解除以外の、債務不履行による解除の場合の違約金については、契約書に「売買代金の〇%」と具体的に定められていることが一般的です。この割合は、売買代金の10%~20%程度に設定されることが多いですが、宅地建物取引業法による上限規制も考慮されます。
違約金以外にかかる可能性のある費用
不動産売買契約の解除は、違約金だけでなく、他にも費用が発生する可能性があります。これらの費用は、契約の進行状況や解除の理由によって大きく異なります。
仲介手数料の精算
不動産売買契約において、不動産会社に支払う仲介手数料は、原則として売買契約が「成立」し、取引が「完了」した場合に発生する成功報酬です。しかし、契約解除のタイミングによっては、その精算が必要となる場合があります。
宅地建物取引業法では、仲介手数料は取引の成立によって請求できると定められています。したがって、契約が解除された場合、原則として仲介手数料を支払う義務は発生しません。しかし、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 手付解除の場合
買主または売主の一方的な都合による手付解除の場合、既に契約が締結されているため、不動産会社は仲介業務を完了したとみなし、仲介手数料を請求する権利が発生していると主張するケースがあります。ただし、実際に支払われるかどうかは、個別の媒介契約の内容や交渉によって異なります。 - 債務不履行による解除の場合
買主または売主の債務不履行により契約が解除された場合も、同様に仲介手数料の請求を巡ってトラブルになることがあります。不動産会社としては、契約締結まで業務を遂行したと主張するでしょう。 - 合意解除の場合
当事者双方の合意により契約が解除された場合、仲介手数料の取り扱いについても合意の中で定めることが一般的です。
一般的には、契約が締結された段階で仲介手数料の請求権が発生すると解釈されることが多いです。しかし、媒介契約書に、契約解除時の仲介手数料に関する特約が記載されている場合もあるため、必ず確認しましょう。
不動産売却時の仲介手数料について知りたい方は「不動産売却の仲介手数料はいくら?計算方法や相場を解説」の記事をご参照ください。
登記費用や税金
不動産売買契約の解除によって、本来発生するはずだった費用が発生しなくなるケースが多い一方で、既に支払ってしまった費用や、契約解除によって新たに発生する可能性のある費用もあります。
特に買主側で発生する可能性があった主な費用と、契約解除時の扱いを以下にまとめます。
費用項目と主な内容、契約解除時の扱い
| 費用項目 | 主な内容 | 契約解除時の扱い |
|---|---|---|
| 印紙税 | 不動産売買契約書に貼付する税金。契約金額に応じて変動。 | 契約書作成時に発生するため、契約解除されても返還されない。 |
| 登録免許税 | 不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記などにかかる税金。 | 登記が実行されなければ発生しない。解除された場合、通常は登記を行わないため不要。 |
| 司法書士報酬 | 所有権移転登記や抵当権設定登記などの手続きを司法書士に依頼する際の報酬。 | 登記が実行されなければ、原則として全額は発生しない。しかし、既に登記申請の準備や書類作成が進んでいた場合、その業務に対するキャンセル料や一部報酬の支払いを求められる可能性がある。 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に一度だけ課される都道府県税。 | 不動産の取得が完了しなければ発生しない。契約解除により取得が完了しないため、原則として不要。 |
| 固定資産税・都市計画税 | 不動産を所有していることに対して毎年課される税金。 | 通常、決済時に日割りで精算される。決済前に契約解除となった場合、買主が負担することはない。 |
これらの費用は、契約が順調に進めば発生するものですが、解除によってその発生が停止したり、一部費用のみ発生したりする点が特徴です。特に司法書士報酬については、既に業務が進行している場合に、作業量に応じた実費請求が行われる可能性があるため、事前に確認が必要です。
不動産投資の税金対策について知りたい方は「不動産投資で税金対策とは?税金対策で法人化のメリットデメリット」の記事をご参照ください。
不動産売買契約の解除手続きと注意点
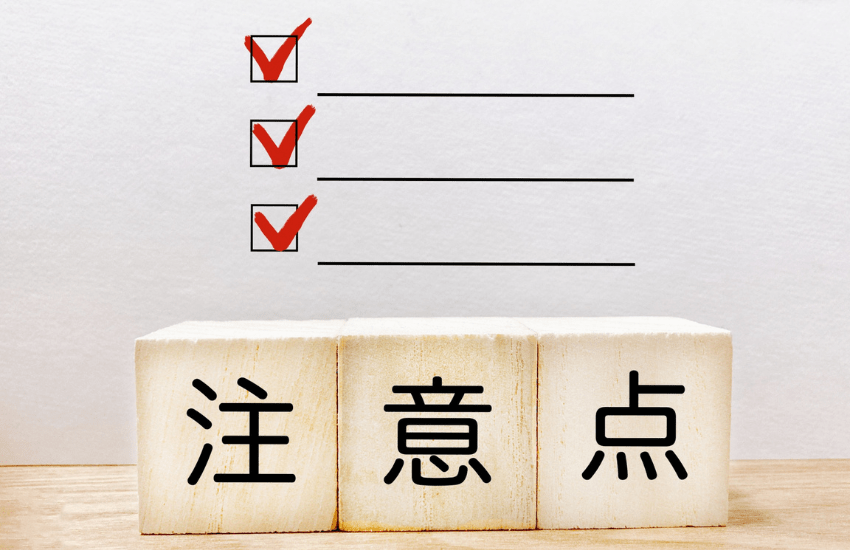
不動産売買契約の解除は、単に「やめる」と意思表示するだけでは完結しません。法的な効力を持つ手続きを踏み、適切なタイミングで実行することが極めて重要です。
手続きを誤ると、意図しないトラブルに発展したり、不要な違約金が発生したりするリスクがあります。
解除通知の方法とタイミング
不動産売買契約の解除は、口頭ではなく書面で行うのが原則です。特に、相手方に確実に意思表示が到達したことを証明するためには、特定の書面を用いることが推奨されます。
解除通知の方法
解除通知は、後々のトラブルを避けるためにも、相手方に確実に到達した証拠を残す方法で行うべきです。最も確実な方法は、内容証明郵便を利用することです。
解除通知書には、以下の項目を明確に記載する必要があります。
- 契約の特定(契約年月日、物件所在地など)
- 解除の意思表示
- 解除の根拠(契約書の条項、債務不履行の内容など)
- 解除の効力発生日
- 違約金や手付金の精算に関する具体的な内容
- 相手方への請求事項(手付金返還、違約金支払いなど)
解除のタイミング
解除のタイミングは、契約の種類や解除の理由によって厳密に定められています。契約書に記載された期限や条件を遵守しなければ、解除自体が無効とされたり、別の違約金が発生したりする可能性があります。
主な解除の種類とタイミングの注意点を以下の表にまとめました。
解除の種類と推奨の通知方法、タイミングの注意点
| 解除の種類 | 推奨の通知方法 | タイミングの注意点 |
|---|---|---|
| 手付解除 | 内容証明郵便 | 契約書で定められた「手付解除期日」までに通知し、手付金を交付(買主の場合)または受領(売主の場合)すること。期日を過ぎると手付解除はできません。 |
| 債務不履行による解除 | 内容証明郵便(催告書、解除通知書) | まず、相手方に相当の期間を定めて履行を「催告」します。その期間内に履行がない場合に初めて解除通知を行います。催告なしの解除は原則として無効です。 |
| 特約による解除(ローン特約など) | 内容証明郵便 | 特約に定められた条件(例:融資承認が得られない)が成就した際、特約に定められた期間内に通知する必要があります。期間を過ぎると特約の適用を受けられなくなる場合があります。 |
| 合意解除 | 合意解除契約書(公正証書推奨) | 当事者双方の合意があれば、いつでも解除可能ですが、書面で合意内容(違約金や費用の精算など)を明確に残すことが重要です。 |
特に、債務不履行による解除の場合、相手方に履行を促すための「催告」を適切に行うことが不可欠です。催告書も内容証明郵便で送付し、その内容と到達日を記録しておくようにしましょう。
不動産売買契約解除の違約金まとめ
不動産売買契約の解除に伴う違約金は、手付解除や債務不履行など、契約内容や解除理由により発生の有無や金額が異なります。違約金以外にも仲介手数料などがかかる可能性もあります。万が一、違約金が発生する状況でも、減額交渉の余地や、ローン特約などの適用で違約金が発生しないケースもあります。
契約前に内容を十分に確認し、問題発生時には速やかに弁護士や不動産会社などの専門家へ相談することが、トラブル回避と最善の解決に繋がります。